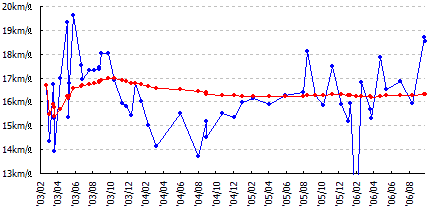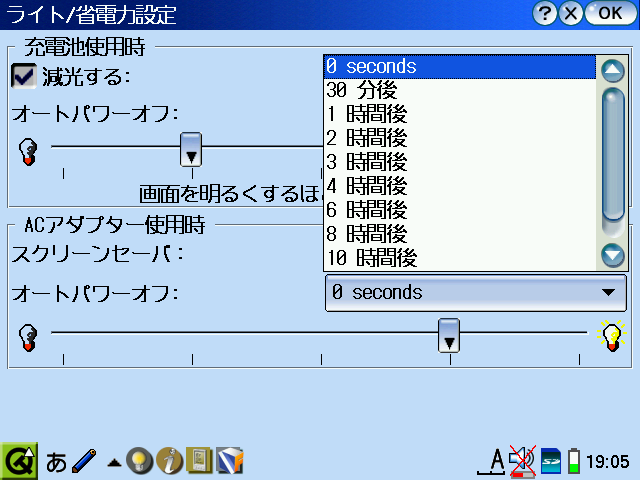[つぶやき]今日の検索
どんなに無茶をやっても「それもありかな」なAjax
http://www.atmarkit.co.jp/fwcr/rensai/ajaxwatch03/02.html
AjaxやWeb2.0に限らず、いろんな形でサービスなどの再利用が簡単にできるようになると、本来の目的とは異なる使われ方も簡単にできるようになって「面白い!使える!」サービスがたくさん出てくる。製作者の意図しないところで役に立つ、そんな事例もたくさん出てくるんでしょうね。
リリース前からブロガーに注目されるFirefox用エクステンション「AllPeers」
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20093962,00.htm
"同社はこのツールがリリースされれば「Firefoxにとって、誕生以来最高の出来事となる」と述べる。"
とあるように、いい意味でも悪い意味でも最高の出来事になるでしょう。
きっとAntinnyみたいなウィルスがはびこって、個人情報が流出して(ry
FirefoxとBitTorrentの威力を合体 友達とファイル共有ができるFirefoxプラグイン「AllPeers」
http://mojix.org/2006/01/04/083028
上記記事に関連して。写真の共有って、キラーアプリになるんでしょうか?
おじいちゃんでも孫でも、誰でも簡単にできるようになったら、キラーアプリにならなるかもしれないですね。自分で撮った写真やビデオを共有するのなら、著作権者と配布する人が同一だから、著作権法的にもOKですしね。配布範囲をしっかりコントロールできれば完璧ですね。
入門篇・ネット時代の「知的生産の技術」(1): 最近の情報フロー
http://d.hatena.ne.jp/umedamochio/20051228/p3
梅田さんの情報収集術。こういうことをオープンにしてしまう梅田さんの度量に感服。この人は若者に対して、シリコンバレーで一流の研究者、経営者になれ!そのためには俺は身を削ってでも応援するぜ!と本気で思っているすごい人なのではないか。
米Google、携帯電話の通信方式に関する特許を取得
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/01/05/10388.html
まじめに考える必要はないのかもしれないけど、たとえば、ある重要な戦略があって、その中の流れのなかででてきたものだとしたら、ヤバいかも。
The Million Dollar Homepage
http://www.milliondollarhomepage.com/
最近いろんなニュースサイトで取り上げられてすごいことになってますね。
じゃあ俺も!ということになりがちですが、でも二番煎じなサイトは、どこも壊滅状態です。
「2005年の大失言」ハイテク・科学界版
http://hotwired.goo.ne.jp/news/business/story/20060105102.html
笑ってしまったけど、2005年で起こったことを振り返る意味でも、なかなか面白い記事かもしれないです。
IBM研究者が語る「身元分析技術」の現状と可能性
http://japan.cnet.com/interview/story/0,2000050154,20092672,00.htm
少し古い記事ですが。プライバシーを侵すことなく個人情報を分析する方法、そんなことができてしまうんですね。偽名で書いているWebページなんて、あっさり見破れるんだろうな。
Ten Rules for Web Startups
http://evhead.com/2005/11/ten-rules-for-web-startups.asp
かなり有名だけど、またこのページにぶち当たったので紹介。
Googleにも10箇条のルールがある↓
Google: Ten Golden Rules
http://www.msnbc.msn.com/id/10296177/site/newsweek/